図面管理システムの選び方、注意点
クラウドかオンプレミスか?スクラッチかパッケージか? 図面管理システム選定のポイント

製造業の設計工程は3次元化が進みましたが、製造工程ではまだまだ図面の必要性が高いのが現実です。
購入部品の見積書、完成品の検査記録など図面以外の文書も多く、図面と関連する文書ファイルが数万点にもおよぶことも珍しくありません。
いまだに紙図面が図面庫(図面キャビネット)に大量に保管されている、紙図面をとりあえずデジタル化してファイルサーバに放り込んだものの有効利用できていない、
という話も、昔に比べると減ったものの、まだまだ耳にします。
DXの推進や、SDGsの一環としてのペーパーレス促進のため、これらを図面管理システムで効率的に管理しようという企業も多くなっています。
一口に図面管理システムといっても、
・Web検索するといろいろなシステムが出てくるのでどれが最適か分からない
・「大は小を兼ねる」で大手企業のシステムを導入したが、実務に合わず稼働していない
など選定に苦慮されているご担当者も多いのではないでしょうか?
以下では図面管理システム選定にあたり、整理しておいた方がよい要件(選び方や注意点)をご紹介します。
図面管理システム選定の参考にしていただけると幸いです。
目次
(1) 運用の目的を選ぶ
(2) オンプレミスか?クラウドか? サーバーの管理形態を選ぶ
(3) パッケージか、カスタマイズか、スクラッチか選ぶ
(1) 運用の目的を選ぶ
図面管理システムをWeb検索するとたくさんのシステムがヒットします。
検索結果を見ると「文書管理システムなら…」「生産管理システム」のような紹介や、PDM、BOM、EDMといったキーワードが書かれています。
図面管理システムはどのような目的に利用したいかで、必要機能や運用法が大きく異なります。
例えば、企業には図面だけではなく、社内規定や業務マニュアル、契約書や稟議書など様々な書類があります。
「全社の文書を管理する文書管理システムで図面も一緒に管理…」と考えて、全社で運用する文書管理システムで図面管理もおこなうと、全社横断のADを利用したユーザー管理機能や、多種多様の文書をカバーするワークフローなど多くの機能を持つ反面、図面には使われない機能も多く含まれる可能性があります。
「図面管理だけでいい」「製造部だけで利用するので、大規模なユーザー管理は不要」という運用であれば、もっと小規模なシステムの方が合うかもしれません。
よく見かけるキーワード別に、目的の例をご紹介します。
■文書管理システム
全社横断規模から小規模なものまで多種ありますが、その主目的は文書管理です。そのため図面管理においてはオプションが必要、または文書管理機能を応用して運用で補うといった傾向があります。内部統制対策としてセキュリティ設定やアクセスログ管理などが充実していたり、テキストベースの全文検索が強力だったりします。
全社横断で文書管理をする中で図面もそれなりに管理したい、ISOなどの内部統制をしっかりしたい、という時に有効なシステムです。
オプションがない廉価な文書管理システムだと、
・大判図面のサムネイルやプレビューが粗い
・図面は全文検索の対象にならない
・テキストでの文書比較機能はあるが、図面は比較対象にならない
ということもありがちです。
また、全社横断規模の文書管理システムだと、
・情報システム部門に入って貰わないとユーザー管理が難しい
ということもあり、一部の部署で導入するには管理が難しいこともあります。
選定時には図面への適応度や運用のためのリソース要件を確認するのがおススメです。
■PDM / PLM
PDM(Product Data Management)は製品設計に関わるデータを一元管理するシステムです。
図面管理だけでなく、BOM(E-BOM)や、設計資料などの文書管理、設計承認のワークフローを兼ね備えます。
BOMを利用し、CADデータ管理(図面管理)だけでなく設計業務全体の統一化、効率化を図る目的ならPDMが適しています。CADとの統合運用を想定した設計部門向きのシステムなので、製造部門等で利用するには費用対効果や難易度が合わないことがあります。
PLM(Product Lifecycle Management)は製品ライフサイクル全体(研究開発、設計、生産準備、生産、調達、物流、販売、メンテナンス)に関わるデータを一元管理するシステムで、全社横断で運用される大規模なシステムです。PDM同様にCADデータ管理(図面管理)の機能も有しますが、あくまでも一部の機能であり、生産管理やE-BOM、M-BOMなど全工程の情報を管理する様々な機能を搭載していて、会社規模で企業競争力を上げるという目標を持って導入すべきシステムです。
■生産管理システム/MES
生産管理システムは納期、在庫、工程、原価といったものづくりに必要な情報を統合し、計画、実行、管理していくものですが、製造工程で図面を利用するため図面管理機能を持っているものもあります。生産管理システムが主なので、図面管理の機能は簡易的なものがほとんどです。
「生産管理も図面管理も!」という場合は、生産管理システムと連動する図面管理専用システムがおススメです。
MES(Manufacturing Execution System:製造実行システム)は生産管理システムの1部で、製造の実行工程を支援するものです。
図面管理が主目的ではないのは生産管理システムと同様です。
■図面管理システム
図面のファイル管理を目的としたシステムなので、図面番号(図番)など図面固有の属性を初期設定で持っていたり、CADから図面情報を直接取得したり、大判図面の閲覧、図面同士の差分比較ができたりと文書管理システムが図面に最適化されたものになっている傾向があります。
部門単位での利用を想定しているので、製造部だけの導入など小規模な運用から開始しやすいシステムです。
近年はファイル管理機能だけでなく、設計資料などの技術文書を図面に紐づけて一元管理したり、ワークフローによる承認ができる図面管理システムも増えており、ちょっとしたPDMのような運用もできるシステムもあります。
図面に特化している分、設計や製造に関係ない文書を管理する汎用性や、会社の基幹システムと連動させる拡張性に欠けることがあります。
(2) オンプレミスか?クラウドか? サーバーの管理形態を選ぶ

サーバーシステムの場合、自社の管理するサーバー設備で運用するオンプレミスか、外部のサーバー設備をインターネット経由で利用するクラウドか選択する必要があります。
クラウド用の図面管理システムの機能が気に入っても、セキュリティ上クラウドに設計データを保管することを許されない企業では、そのシステムを導入することはできません。ですので選定前の早い段階で必ず確認が必要です。
導入を決定した後で、情報システム部門ともめるケースもあるので早めに抑えておきたいポイントです。
■オンプレミスの特長
オンプレミスはサーバーやバックアップシステムなどの初期費用が高額になりがちです。
サーバールームの運営費や、管理者の人件費など管理コストもかかります。
サーバーやバックアップシステムなどの機器の購入(リース)期間も必要なので、導入に要する期間は長めです。
万一の災害発生に備えた対策も自社で行う必要があり、BCPを策定していないと、復旧に非常に時間がかかる場合があります。
機材の運用にコストがかかる反面、LAN接続のため通信速度が速く、安定した稼働が期待できます。
オンプレミスの図面管理システムはカスタマイズできるものも多く、基幹システムと連動した自社専用のシステムを構築することができるものもあります。
自社でデータを管理しているので安心感はありますが、セキュリティ対策は自社で行う必要があります。
オンプレミス=セキュリティが堅牢というわけではないので注意が必要です。
■クラウドの特長
クラウドは、クラウドサービス提供事業者が用意している機器を利用するので初期費用が安価で、契約後すぐに利用を開始できるメリットがあります。
運用形態によってはランニングコストがかさむこともあるので、必ずしも安価とは言い切れませんが、サーバー管理の人件費等を考えると費用も抑えられる傾向にあります。
災害対策もクラウドサービス提供事業者で行っている場合が多いですが、念のため契約前に、災害対策をおこなっているかは確認しておくほうがよいです。
データはクラウドに置かれるため、特に機密性の高い設計データを外部の業者の手に委ねたり、インターネットを経由してデータが流れることを危惧する声もあります。クラウドサービス提供事業者側でもセキュリティ対策をしているので、クラウド=セキュリティに不安があるという事はありませんが、万一を考えてクラウドの使用を許可していない企業もあります。
■オンプレミスとクラウドの特長比較
| オンプレミス | クラウド | |
|---|---|---|
| 機材/設備 | 自社管理 | 提供事業者管理 |
| ランニングコスト | 管理人件費/機材保守費/電気代等等で割高 | 利用量によるが安価 |
| 導入期間 | 機材/設備の準備期間が必要 | 契約後すぐ |
| 通信速度 | LANの状態によるものの安定的で高速 | サーバやインターネットの状態に依存 |
| データ管理 | 自社管理 | 提供事業者に依存 |
| 拡張性 | 自由度あり | 制限あり |
(3) パッケージか、カスタマイズか、スクラッチか選ぶ

図面管理システムを導入する際に直面するのが、今までの自社で構築した図面運用ルールが、図面管理システムの通常の機能では実現できないという問題です。
どうしても従来までの運用を再現したい場合、図面管理システム側をカスタマイズするしかないのですが、要望事項が多いと1から作った方が早いということで、スクラッチ開発してしまうことも考えられます。スクラッチは完成すれば便利な反面、システムベンダーに完全に依存してしまうのでベンダーの事業継続性がリスクとして織り込まれます。得てして保守費や改修費等も割高になりがちです。
スクラッチは割高なので、妥協する点は妥協して、パッケージをベースにカスタマイズするという方法もあります。開発費や、コンサルティング料などで初期費用が増加するほか、保守費がカスタマイズ部分にも掛かることがあり、カスタマイズの規模によっては費用が高くなる傾向にあります。
属性項目など決められた項目以外はカスタマイズしないパッケージを導入すると、運用方法は図面管理システムが持つ基本機能に寄せなければいけませんが、導入コストやランニングコストを抑えられます。
スクラッチやカスタマイズを前提にする場合、費用だけでなく開発期間もかかるので、計画的な導入が必要となります。図面管理システムを選定した後で、カスタマイズ費用で開発期間や導入コストが大幅に増えてしまった、ということにならないようあらかじめパッケージ中心でいくか、スクラッチ開発するかを想定して選定する方がスムーズです。
ご紹介した以外にも選定にあたってのポイントや注意点はありますが、事前に
・どのような目的で
・どのような規模で
・どのような立場の人が
・どのようなシステム要件で
・どれくらいの予算で
利用するかを決めておくことで、スムーズな選定をおこないやすくなります。

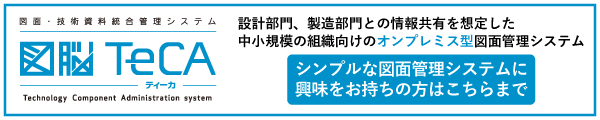
画像・映像のことなら
フォトロンにお任せください
お問い合わせは
こちらから
株式会社フォトロンに関する
お問い合わせはこちらから
資料を
ダウンロード
フォトロンおよびグループ企業の
会社紹介資料をダウンロードできます
