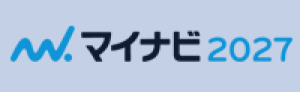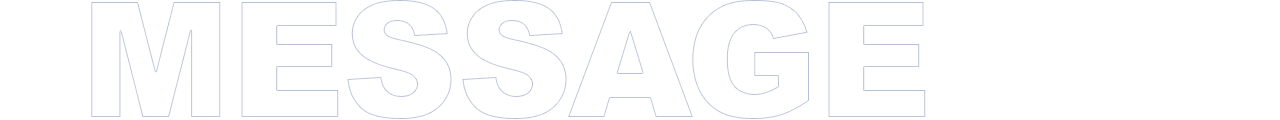

社長メッセージ
時代に即した提案を積極的にできる人を求めています
ハイスピードカメラや映像関連システムを中心に事業分野を広げ、成長を続けているフォトロン。社長の瀧水隆に、自身の経験と会社の展望を交えながら、求める人材について聞きました。
Q フォトロンの魅力について教えてください。
“最先端”にチャレンジできるステージがフォトロンです。
私たちはハイスピードカメラなどを製造・販売するメーカー的な側面もあれば、海外の優れた映像システムなどを輸入してシステム提案するSIer的役割も担っています。また、CAD関連ソフトウェアなどの開発スタッフを抱えるソフトウェア会社としての側面も持っています。そのうえ、アメリカ、ヨーロッパ、中国、ベトナムに海外現地法人を置いた、世界市場を相手にしている企業なので、いろいろチャレンジできる会社です。
取引先には大手自動車メーカーや某公共放送局など国内外でも名が通っている企業や大学、研究機関が多く、たとえばNASAにも製品を納めています。大学の授業をサポートする映像関連システムも扱っています。最先端のモノづくりや次世代の人材育成という重要な取り組みに、間接的に携わってもいます。納品した製品・システムのポテンシャルを100%発揮させるため、当社では納入後もサポートメンバーとしてお客様に関わり続けます。その意味では、当社の営業は単なるモノ売りではなく、技術営業です。サイエンティフィックな意味で社会貢献していると言えるかもしれません。これはフォトロンの社員だからこそ味わえる醍醐味であり充実感です。
Q 求める人材像について教えてください。
好奇心が旺盛で知識にどん欲な人をお待ちしています。
最先端のモノづくりをしている人たちが商談の相手ですから、それなりの知識と専門性を必要としますが、それらは指示をこなしているだけでは身につきません。自らの力でモチベーションを高め、いろいろな物事に興味を示し、どん欲に知識を吸収していく人が当社にとけ込みやすいと思います。
特に近年は動画配信サービスやクラウド、メタバースなど、当社が関わっている世界でも次々と新しい動きが出てきています。そのスパンも非常に短く、そうした流れに乗って時代に即した企画・提案ができるのは、やはり若い人たちです。そういう意味で「好奇心」が強く新しいガジェットに興味をもち、積極的に提案をしてくれる人材を求めています。
Q 仕事をする上で大切なことは何ですか?
仲間をつくることで人生もビジネスも可能性を広げます。
ビジネスの世界は、一人では何もできません。同じ方向性の仲間が協力し合って、初めて当社の製品・システムも生まれ、最先端のモノづくりのサポートが可能となります。戦う相手は競合他社であって、社内の人間ではありません。私自身、フォトロングループ内の人間はすべて仲間であり、決して社内に敵はつくらないという信念のもとで働いてきました。この「仲間意識」を大切にできることも、「好奇心」とともにフォトロンの社員に求める重要なキーワードで、それは私の経験から導き出された信念でもあります。
Q これまでで印象深い出来事は何ですか?
親会社倒産はマイナスではなく進むための“推進力”でした。
私が社会人になったのは1983年の春で、入社したのは中堅商社でした。フォトロンはその子会社として設立された会社で、設立と同時に私は出向になりました。ところが、翌年の2月にこの親会社が倒産してしまったのです。しかし、その危機をフォトロンが乗り越えられたのは、当時在籍していた約20人の仲が良く、危機を乗り越えようとする同じ志をもった社員がいたからです。私自身、それが決め手となって正式な社員として残ることを決断し、現在に至るわけです。もっとも、当時は先輩を頼ってばかりもいられない状況で、必死になって知識の吸収に努め、徐々に戦力としての自信を備えていきました。
Q 今のご自身を支える経験は何かありますか?
2度のアメリカ駐在で得た人間関係は今でも私の財産です。
最初は32歳から4年間、シリコンバレーに赴任したのですが、駐在員は私一人で英語もほとんど話せず、ましてや現地でのフォトロンの知名度もほぼない状況のなか、自らがアンテナを張って食らいついていかないと、状況は何ら変わらないのだと思い知らされました。
また、そこでも実感したのが仲間の大切さです。挨拶の仕方から飲み会の雰囲気づくりまで、さまざまな面で支えてくれたのが現地採用のスタッフです。アメリカ人は考えていることをストレートに言いますが、こちらからもストレートに指示や判断の理由を説明すれば、理解してくれます。後に40歳から10年間、再びアメリカに駐在しましたが、帰国する際に現地のスタッフが送別会を開いてくれて、iPadと名前入りの時計をプレゼントしてくれたのは忘れられない思い出です。こうした出会いを、フォトロンに入社する人たちに、ぜひ経験して欲しいと思います。
Q 今後の事業展開について教えてください。
トップ企業をサポートしながら私たちと共に成長しましょう。
今まで以上にグローバルに展開していく予定で、どれだけ事業領域を広げられるかがひとつの鍵だと考えています。そのためには、新しい技術やツールを取り入れなければなりません。技術革新のテンポが速くなっているなか、若い世代の社員の活躍が不可欠なのは述べたとおりです。当社の製品・システムで、間接的に未来の社会づくりをサポートしているのだという自負を持ちつつ、積極的な提案を期待しています。
会社としても、グロービスのオンライン動画サービスを受講できる環境を整え、開発担当者には各種セミナーの受講や社会人ドクターとして博士号の取得を推奨してきましたが、これからは、さらに人材育成に力を注いでいくつもりです。一方で、世界のトップ企業のモノづくりをお手伝いしながら、未来の社会像を勉強し、会社も社員と共に成長していきたいと思います。



執行役員メッセージ
夢にまい進できる「自律」した人に扉を叩いて欲しい
本社オフィスのリニューアルを敢行など、時代に即した働き方へ進化し続けているフォトロン。執行役員の城敬之に、現状と求める人材について聞きました。
Q 現在の働き方について教えてください。
当社では「効果・効率・共創」をキーワードに、出社とリモートワークを柔軟に組み合わせたハイブリッドな働き方を継続しています。
コロナ禍を経て一気に進んだリモート体制の整備は、もはや「非常時の代替手段」ではなく、日常の働き方の選択肢として定着しました。現在もテレワーク率は全体で約44%を維持しており、業務特性や個人の状況に応じて最適な働き方を選択しています。特に、開発系はテレワーク中心の勤務が多く、一方で営業や製造・管理部門は、対面でのコミュニケーションや現場対応が求められる機会が多いため出社の比率が高くなっています。2024年には本社オフィスの全面リニューアルを行い、フリーアドレス化・ABW(Activity Based Working)を導入しました。これにより、社員は「集中」「協働」「発想転換」など、業務内容や目的に応じたスペースを選びながら働くことができるようになり、出社の価値がより明確になっています。また、育児・介護との両立や、通勤ストレスの軽減といった面でも、柔軟な働き方が社員のエンゲージメント向上に寄与しており、個々のアウトプットやチーム全体のパフォーマンスも高い水準を維持しています。一方で、ハイブリッドワークの前提となるセキュリティ意識や情報リテラシーの向上も重視しており、定期的なeラーニングやリスク管理研修を通じて、社員一人ひとりの意識と自覚の向上はもとより、安心・安全に業務を遂行できる体制づくりにも注力しています。
Q 社員の評価・育成方法を教えてください。
社員一人ひとりの成長と組織の成果を両立させるために、タレントマネジメントシステムを活用し、評価・育成・配置を一体的に運用しています。
目標管理(MBO)や人事評価だけでなく、自己申告やスキルマップ、キャリア志向の把握もデジタル上で行っており、データに基づいた継続的な育成を可能にしています。マネージャーはこの情報をもとに、日々の業務を通じたフィードバックやミーティングでの対話を重ねながら、個々のメンバーの成長を支援しています。また、近年ではラーニングプラットフォームを通じた自律的な学習機会の提供にも力を入れています。社内外を問わずスキルをアップデートし続けられる環境を整えることで、「成長し続けられる会社」であることを目指しています。さらに、「評価=報酬」だけではなく、「評価=対話と成長機会」と捉え直し、若手社員やキャリア採用者にも納得感を持ってもらえるよう、人事制度の透明性向上と運用の丁寧さを目的として、2024年に人事制度を刷新した上であらたな運用を開始しました。
Q 求める人材については、いかがですか?
私たちが求めるのは、「自ら考え、行動し、チームと成果をつくっていける人」です。
当社は、「顧客満足による信頼の創造」「お客様の業務効率向上に貢献」「画像にこだわる会社」という企業理念のもと、変化の激しい社会の中でも、技術と発想で価値を提供し続けてきました。その根底には、社員一人ひとりの「自分の夢や目標に向かって努力する姿勢」があります。働き方が多様化した今、自らの働く環境や時間の使い方を主体的にデザインする力がより重要になっています。どこで働くかよりも、「どのように働き、何を生み出すか」が問われる時代。自ら目標を立て、必要なスキルを学び、仲間と協力しながら成果に結びつけていく力を大切にしています。加えて、今後の事業成長においては「DX」「自動化・AI」「サステナビリティ」「グローバル連携」といったテーマがますます重要になってきます。こうした領域に自然と興味関心を持てる、デジタルネイティブ世代の感性や発想力に、大いに期待しています。もちろん、語学や異文化理解といったスキルもあれば歓迎ですが、それ以上に「多様な価値観を受け入れ、他者と協働する姿勢」が大事だと考えています。
Q 就活生へのメッセージをお願いします。
就職活動は、これからの人生を考えるうえでとても貴重な「自分と向き合う時間」です。
だからこそ、不安になることもあると思いますが、ぜひ前向きに、そして楽しみながら取り組んでほしいと願っています。会社の規模や知名度ではなく、「自分がどんなふうに働き、どう成長していきたいか」という軸を大切にしてください。そして、その軸に合いそうな会社をいくつか見つけて、深く対話してみてください。選考というより「相互理解の場」として、会社の中にいる人の価値観や考え方に触れてほしいのです。私たちも、みなさんと誠実に向き合いながら、未来の仲間となる方との出会いを心から楽しみにしています。そして、もしそのひとつにフォトロンを加えてもらえたなら、こんなにうれしいことはありません。